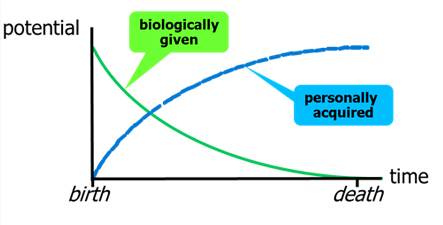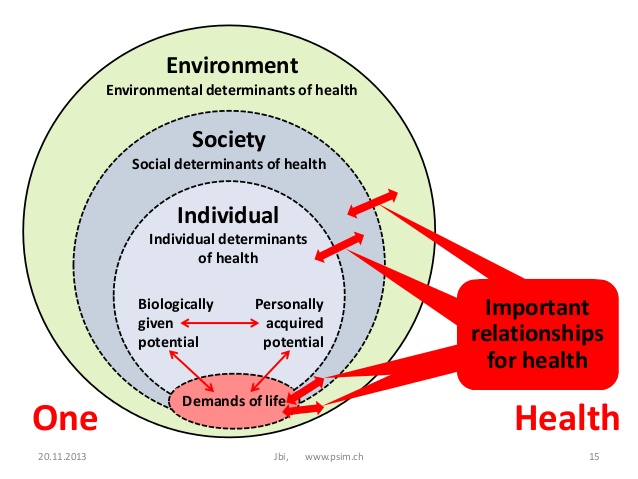専門職連携実践が注目されているわけ
専門職連携実践:Interprofessional work(以下IPW)は日本の医療・介護・福祉の領域において、現在ブームになっているといってよいでしょう。昔からチーム医療は大事だと言われ続けてきているわけですが、改めてIPWが日本の医療で注目されている理由として、以下の2点に注目すべきでしょう。
1.医療の高度化、細分化、分業化が急速に進行すると同時に、医療の安全性と質の保証への要求水準が高くなってきていること。
2.超高齢社会を迎えつつある地域のなかで、身体心理社会倫理的な要因がからみあう複雑で困難な健康問題にチームで取り組む機会が急速に増加してきたこと。
医療はもともと多くの領域の異なる専門職により担われてきましが、従来それぞれの専門職は独自の知識技術構造と教育システムをもち、一定の排他的な世界を構築してききたわけです。しかし、上に述べたような状況下では、従来の専門職のあり方では適切に対応できない場面が多くなってきています。そうした理由として佐伯*1は以下の3つの限界性をあげています。
1.個人で仕事を行うことの限界性:医療技術の複雑化、細分化の中で自分の専門領域のみで治療・ケアを行うことは不可能になってきている
2.専門職種の縦割りで仕事をすることの限界性:専門職間の連携不全が医療事故やケアの質の低下につながることが認識されている
3.患者の問題領域を一つに絞って仕事を行うことの限界性:疾病のみでなく生活する人として患者や家族をとらえケアすることに、医療のパラダイムがシフトしてきている
例えば、医師という職種には「主治医としてすべての責任を負い」「他の専門職種へ権限は移譲せず」「患者の生物医学的側面だけをとりあつかう」といった傾向が従来から強いとされてきました。しかしながらSabaら*2は、そうした伝統的な医師のモデルをLone physician model(孤高の医師モデル)と呼び、それはすでに現代の医療においては神話にすぎないとして、「協働」と「連携」そして「患者中心性」を軸としたあたらしい職業モデルが必要であると主張しています。そして、これは日本においても適用できる視点だと思います。
IPWと価値対立
以下の2つのケースを読み、どんなタイプの対立や葛藤が生じているか考えてみてください。
ケース1
誤嚥性肺炎を繰り返す高齢認知症患者が入院している。担当医はさらに抗菌薬治療を続け、胃瘻造設を考えている。家族もそれなりに治療をつづけてほしいといっている。しかし、これまでの入院ケアを担当してきた病棟看護師たちは、比較的コミュニケーションのとれていた状態で患者本人が話していたライフヒストリーをよく知っており、これでいいのか?と疑問を持っている。
ケース2
久しぶりの休暇予定だった若い医師が、その当日の外来担当医師の体調不良で、急遽外来診療をやることになった。急に欠勤となった医師はしばしば「体調が悪い」とのことで診療を穴をあける問題医師であった。イライラする気分を医師はコントロールできないし、次々と予約外の患者がやってくる状況である。「今日は臨時対応だから予約以外はことわってくれ」と看護師に伝えた。窓口で予約外患者が看護師に大声でクレームをいっているのがきこえる。看護師は「先生からそのような指示をもらっているので、申し訳ありません」と答えている。
専門職連携実践にはつねに葛藤と対立がつきものです。さらに言えば、おそらく連携とは対立の自覚化と解決の不断の連続がその本質であるともいえるのではないでしょうか。
実際の医療場面では仕事をスムースにすすめるために、職種間あるいはチームメンバー間の対立をそれをまあまあと水にながしたり、棚上げにしたり、隠したりすることがある種の「スキル」として、従来も求められてきたと言えるかもしれません。そうした状況は、医師を頂点とした各種権威勾配があり、またかく職種内にさまざまなヒエラルキーが存在することで可能になっていたと思います。
ところで、チームメンバーのなにが対立するのでしょうか?
それは価値の対立であるといっていいと思います。
この価値はチームメンバーの個人的な価値観、そしてその背景となる職場価値、社会価値体系に由来するものもあれば、チームメンバーの属する職種における価値体系によるものもあります。そして、チーム医療では個人対プロフェッショナル、個人対個人、プロフェッショナル対プロフェッショナルといった様々な価値対立がキメラ上に存在しているというふうに思います。
上記のケース1においては、おそらく医療自体の目的に関する医師と看護師のプロフェッショナルとしての価値対立が、対立構造の重要な側面を構成しています。ケース2においては、医師の個人の価値観と看護師や事務職員のプロフェッショナルとしての価値観、権威勾配にもとづくメンバーの内的葛藤が生じているでしょう。
付け加えれば、これらの事態が、さらなる混乱を招いたり、状況がさらに悪い方向へ向かった場合も考えられますが、事態がそれなりに収拾したあとに、安全な環境で事後的にふりかえることで、チームの連携力の成長に繋がる契機にすることができるはずです。
個人の価値観の多様性
ところで、チームメンバーの個々の価値観はきわめて多様性に富んでいるという前提に立つ必要があります。
まず、平均的な日本国民としての価値観(むろん海外出身、あるいは外国籍のメンバーの場合は異なった価値観をもっているでしょう)があるでしょうし、個々のメンバーの生育史、生活史に由来するユニークな価値観もあります。たとえば以下の◯◯にどんな言葉を当てはめるかは、メンバーごとに相当なバリエーションがあるはずです。
- 人間の生きがいとは◯◯である
- 仕事とは◯◯のためにやるものである
- 人が死ぬということは◯◯なことである
- ◯◯は言葉ではつたわらない
- 家族とは◯◯であるべき
- 親の責任は◯◯である
- こどもは親に対して◯◯であるべき
こうした個人の価値観は臨床上の価値判断において、実は大きな影響を与えるものです。そして、それらが、しばしば自分自身のプロフェッショナルの価値観と対立する場合もあります。たとえばある医療従事者が「もし家族メンバーが病気になったなら、なにはなくても駆けつけるべきであり、それは仕事に優先するものではないし、それが本当の家族だろう」という価値観をもっている場合、見舞いにあまりこない患者家族は、「まともな家族ではない」と感じている可能性があります。こうした個人的な価値観に基づく感覚や印象が臨床判断にバイアスをもたらす可能性は十分あることは容易に予測されるでしょう。
実際には、家族のあり方はきわめて多様性に富んでおり、「正常」のレンジは相当広いと考えるべきです。そして、恵まれた家庭環境で育ってきた若い医療者の家族像の許容範囲はしばしば狭小すぎる傾向があります。
プロフェッショナルとしての価値観
次にプロフェッショナリズムについて考えてみたいと思います。
一般的にすべての医療プロフェッショナルに共通のコアとなる価値は以下に列挙するようなものだと思いますが、実際には個人個人でこれらの捉え方や行動化は相当違うものです。
- まず害をなさないこと
- シンプルをよしとする
- 正直であること
- みんなで協力しあって行動する
- バランスよく行動する
注意すべきなのは、職種が同じなら共通のプロフェッショナルとしての価値観を共有しているわけではなく、たとえば医師においても個人の価値がプロフェッショナルとしての価値体系にビルトインされていることがおおいものです。たとえば、どうすれば良いケアになるかを看護師と議論している時に、ケアのプロセスを重視する看護師に対して「要はなおればいいんでしょ。なおるようにやればいい。思いへの配慮とかっていう主観的なものでぐだぐだと議論するのは無駄だよ」という医師の発言はプロフェッショナルとしての「価値」対立の露呈なのだが、同時に、この医師のプロフェッショナルとしての価値観の個人へのビルトインの仕方の多様性も明らかにしてしまっています。
職種ごとに倫理指針が各職能団体*3*4から発表されていますが、職種ごとのプロフェッショナルとしての価値とはこうした倫理綱領より幅広く、言語されていないものもあると思います。
たとえば一般的に医師は疾患の治癒(Cure)に価値をおき、看護師は患者のQOLの向上(Care)に価値をおくといわれますが、事態はそう単純ではなく、実際にはCare重視の医師もいるし、Cureを重視するセラピストも多いです。これらの個々のプロフェッショナルとしての価値観は実際の診療活動でプランや行動に具体的にビルトインされますが、それとして自分が意識していることは少ないものです。むしろ、前に述べたようにチーム内に生じる違和感や対立に関するやりとりを通じてそれが露呈することが多いという印象をもっています。そして、そこにこそ、効果的なIPWを促進するためのキーポイントがあるのではないでしょうか。
IPWにおける価値のマネージメントの実際
さて、質の高いIPWのためには、チーム内コミュニケーションをいまいちど見直すことが重要です。なぜなら、日常的なチーム内のコミュニケーションを円滑におこなえることが、価値対立を見出し、解決するための条件だからです。
まず定期的なチームのミーティングの時間を保証することです。この時に、多職種で学習をすることが有用です、成人教育の観点からすると、実際のケースの検討を通じた、多職種による問題基盤型学習の形式をとるとよいと思います。これを通じて、自分以外の職種の専門性に関して、彼らの役割、価値観、問題にかんしてどのようなアプローチをするのか、あるいは問題にたいして、どこまでできるように教育されているのかといったことを知ることができるようになります。たとえば、セラピストがどのような教育課程を経ているのか、管理栄養士教育におけるカウンセリングスキルに関するアウトカムはなにか、そもそも看護学という学問はどのような体系なのか、といったことに答えられる医師はほとんどいないでしょう。しかし、それが重要なのです。逆に医師がオールマイティなスキルをもっているという幻想をいだいている他職種メンバーもいるかもしれないのです。
これと関連して、個々のチームメンバーが他のチームメンバーに対して何を期待しているのか、その内実について共有することが大切です。たとえばあるメンバーが「ベストを尽くしたい」というときの「ベスト」とはなにか。それは個人によって定義やイメージが違う可能性があります。こうしたお互いへの期待は仕事の引き継ぎをたのむときに問題になることが多いです。情報の手渡しのスキルはつねに向上させる必要がありますが、情報の手渡しのコツは、伝える相手にどのようにして欲しいかを映画のように頭のなかで再現できるような、具体性をもった内容を伝えることです。
また、一般的チーム内コミュニケーションの促進をはかるために、一緒に昼食を取るなど。時間を確保して、落ち着いた雰囲気で「仕事以外のこと」について話し合うことにより促進されるでしょう。チームが一緒に昼食をとったり、仕事後に職場内でパーティをしたりすることは有意義です。
相互フィードバックの文化
上述したさまざまな方略のインフラとして、チームメンバー同士のフィードバックの文化を醸成することが必要です。相手にフィードバックするスキルはすべての職種に重要です。
効果的なフィードバックの一般原則として以下のポイントに留意しておきましょう。
1. 相手の人格ではなく、具体的な行動に対して評価するという姿勢を保つ。これを可能とするのがNo blame cultureである。
2. 推測や噂ではなく、具体的な情報や事実に基づいて行うこと。
3. 相手の失敗や弱点だけでなく、かならずうまくいったところ、強みについても同時に評価すること。
4. 相手がこのチームにどのように貢献しているかをチームメンバーで共有すること。
5. 次回はどのようにすればうまくいくか、どんな学習が今後必要なのかといった、前向きの議論に時間をかけること
6. 発言は一般的に、「私は◯◯と思う、考える」というように自分を主語にして発言するこころがける。「一般的にいうと・・・」や「世の中では・・・」といった相手への評価の主体が不明確なフィードバックは効果的でない。
フィードバックはなんとなくできるようになるというようなものではなく,かなり意識的にとりくまないと,自然にはできるようにならないものです。
まとめ
IPWにおいて、価値の対立とそのマネージメントは、チームの協働が有効に行われるためのキーになります。コミュニケーションのインフラをきちんと作りながら、対立や葛藤を明らかにし、チーム全員で考え、対応していく文化を形成できれば、IPWの質は不断に向上していくことになるでしょう。
このエントリーは、新興医学出版社モダンフィジシャン(Modern Physician) 2016年No.5に寄稿した記事に加筆訂正したものです。